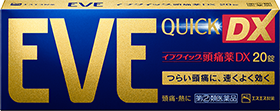市販の頭痛薬(解熱鎮痛薬)の基礎知識や選ぶ際のポイント
頭痛が起きてしまったときは、症状を改善させるために
市販の頭痛薬(解熱鎮痛薬)を用いるのも1つの方法です。
緊張型頭痛の場合は運動したりリラックスしたりして
筋肉の緊張をほぐすようにしましょう。
本コンテンツでは正しく上手に解熱鎮痛薬を活用するために、参考となる基礎知識を紹介します。
市販の頭痛薬(解熱鎮痛薬)の
成分と鎮痛効果の関係

OTC医薬品(市販薬のこと)の頭痛薬(解熱鎮痛薬)には、医療機関で処方される解熱鎮痛薬と同様の有効成分が配合されており、痛みや熱をおさえてくれます。解熱鎮痛薬の有効成分には、大きく分けると「NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)」と呼ばれるものと、そうでないものがあります。
頭痛のセルフケアには「NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)」がおすすめ
頭痛のつらい人が15才以上の場合、頭痛のセルフケアには、市販の非ステロイド性抗炎症成分配合の頭痛薬が有効です。痛みのもととなるプロスタグランジンという物質の生成をおさえ、頭痛を和らげる効果が期待できます。
非ステロイド性抗炎症薬は、英語の Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs の略として「NSAIDs(エヌセイズ)」とも呼ばれます。
市販の頭痛薬に含まれる代表的な成分には、プロスタグランジンの生成をおさえて、炎症・痛み・熱をおさえるイブプロフェンやアスピリン(アセチルサリチル酸)といったNSAIDsに分類される成分がある一方で、中枢性の作用で痛み・熱をおさえるが、抗炎症作用がほとんどない(NSAIDsではない)アセトアミノフェンなどもあります。
なおNSAIDsであるイブプロフェンは、抗炎症作用が強く、また胃腸障害の副作用が比較的少ない成分です。もともとは病院で処方される医療用医薬品として開発された成分ですが、日本では1985年から、OTC医薬品として販売されています。
プロスタグランジンとは?
体内でさまざまな働きをしている生理活性物質です。ある種のプロスタグランジンは組織が刺激を受けたときに生成され、局所で痛みや炎症を引き起こすほか、体温調節中枢に作用して体温上昇(発熱)を起こすことが知られています。
「NSAIDs」にあたる有効成分
「NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)」は、熱や痛みを速やかにおさえてくれます。ただし一般的に知られる副作用として、胃粘膜への刺激や血液の凝固のほか、腎臓や肝臓、心臓などの機能に影響を与える場合があります。また、インフルエンザ治療に際してのNSAIDsの服用については、慎重に判断を行うべきと考えられています。
「NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)」に分類される代表的な有効成分には、以下のようなものがあります。
- イブプロフェン
- プロスタグランジンの体内での生成をおさえ、鎮痛や解熱、抗炎症作用をもたらします。頭痛のほか、生理痛や関節痛、のどの痛みの緩和にも用いられ、総合感冒薬にも配合されています。
注意点として、主に症状を一時的に和らげる目的(対症療法)として使われるものであるため、症状が改善しないときや、逆に痛みがまったくないときなどに漫然と服用することは推奨されません。
人によっては胃腸障害や、腎機能・肝機能の悪化、めまいといった症状があらわれる場合が考えられます。ただし、イブプロフェンは比較的、胃への影響が少ないNSAIDsとして知られています。市販薬の場合、服用は15才以上からとなっています。 - アスピリン(アセチルサリチル酸)
- 抗炎症作用、鎮痛作用、解熱作用をもちます。発熱に用いられるほか、プロスタグランジンが関係すると考えられる頭痛や関節痛、筋肉痛の緩和のためにも使われています。
また、上昇した体温調節中枢の設定温度を正常な状態まで戻し、熱放散を促進して体温を正常化する作用もあります。
注意点として、アスピリンは胃粘膜への直接的な刺激作用をもつことから、胃腸障害の副作用が考えられます。特に胃腸の弱い人は空腹時の服用を避けるほか、必要に応じて胃粘膜保護剤の併用が推奨されます。なお、15才未満の人は服用できません。 - ロキソプロフェン
- プロスタグランジンの生成をおさえ、解熱、消炎、鎮痛作用をもたらします。頭痛のほか、腰痛や肩関節の痛み、抜歯後の鎮痛や消炎のためにも使われます。15才未満の人は服用できません。
注意点として、ロキソプロフェンはOTC医薬品では第1類医薬品に該当するため、薬剤師がいる店舗で薬の情報提供を受けてから購入する必要があります。
「NSAIDs」ではない有効成分
「NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)」ではない代表的な有効成分には、アセトアミノフェンがあります。
- アセトアミノフェン
- 解熱・鎮痛薬成分の1つであり、脳の体温調節や痛みを感じる中枢へ作用します。総合感冒薬(かぜ薬)のほか、小児用の解熱鎮痛薬にも配合されています。
注意点として、消炎(抗炎症)作用はほとんどないため、発熱や痛み、腫れなどの症状への作用は比較的緩やかです。
市販の頭痛薬(解熱鎮痛薬)の
選び方
市販の頭痛薬を選ぶときには、薬局やドラッグストアなどの薬剤師・登録販売者に症状を相談しながら選ぶことが大切です。相談時や、自分で検討するときの参考となる基礎知識を紹介します。
効き目の「速さ」と「効果」を重視する
つらい頭痛の症状は、少しでも早めにおさえたいものです。痛みがひどくなると、痛みが痛みを呼ぶ現象が起こることがあります。プロスタグランジンの生成をより早く効果的におさえるために、本コンテンツでご紹介しているような「NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)」も選択肢に入れつつ頭痛薬を選びましょう。
日常的な頭痛に悩まされていても、我慢できるうちは薬に頼らない方がよいと思っていませんか?「痛み止め」は、痛みが本格的になる前に服用することで、原因物質(プロスタグランジン)が増えてしまうことをおさえ、痛みを和らげやすくします。飲むのが遅れてしまうと、薬が効きにくくなってしまう場合もあります。
特に胃腸が弱い人は「胃にやさしい」工夫がされた薬を選ぶ
プロスタグランジンには種類があり、痛みのもとになるプロスタグランジンとは別に、胃の粘膜を守るプロスタグランジンがあり、その生成をおさえると、胃に不調が生じる可能性があります。胃の粘膜を保護し、胃が荒れるのを防ぐ工夫がされた頭痛薬もあるので、利用するのもよいでしょう。
こういうときは
「市販の頭痛薬(解熱鎮痛薬)」を飲んでいいの?
こんなときは市販薬の服用前に担当医師や薬剤師、登録販売者へ相談!
- ・医師、歯科医師の治療を受けている最中
- ・妊娠している、妊娠している可能性がある
- ・授乳中
- ・高齢者
- ・薬などでアレルギー症状を起こしたことがある
- ・心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍などの診断を受けている
こんなときは市販薬の服用を控えて!
- ・直後に乗り物や機械などを運転操作する予定がある(鎮静成分が入っている市販薬の場合NG)
- ・同じ薬、あるいは同じ成分で過去にアレルギー症状を起こしたことがある
- ・同じ薬、あるいは他の解熱鎮痛薬やかぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある
上記は、一般的な市販の頭痛薬(解熱鎮痛薬)服用における注意事項の代表例です。市販の解熱鎮痛薬を服用する際には、必ずその薬ごとの注意事項を正しく確認するために、添付文書にしっかり目を通しておきましょう。
エスエス製薬の製品は、薬ごとに添付文書のダウンロードが可能です。
「市販の頭痛薬(解熱鎮痛薬)の効果が
追い付かない可能性がある」のはどんなとき?
市販薬を飲んでも効いていない気がする、思うように効果が感じられない、というような場合には、以下にあてはまらないかをまず確認してみましょう。
服用のタイミングが遅い場合
解熱鎮痛薬の服用タイミングが遅くなり効かなかったという場合、次回から早めに飲むことで解決するケースがあります。具体的には、頭痛を感じてからしばらくの間「なるべく薬を飲むのはやめておこう」と我慢した場合などです。
痛みを長時間我慢してしまうと、その間に痛みの原因物質であるプロスタグランジンが生成されてしまいます。痛み止めは本来この生成を抑制するものですが、生成された後から痛み止めを使っても、効きにくい場合があるためです。
市販の解熱鎮痛薬は、痛みを感じたら早めに服用しましょう。
単に我慢という理由でなくとも、例えば以下のようなときに解熱鎮痛薬を飲むことを控えてしまう人がいらっしゃるようです。それぞれのケースについて、判断の仕方を紹介します。
- 生理期間中だったので、服用しないほうがよいと思った
- 【アドバイス】基本的には、生理期間中の頭痛や生理痛の対処として解熱鎮痛薬を服用しても問題ありません。症状に応じてご使用ください。
- 食後すぐに薬を飲むと、薬の成分の吸収が悪くなると思った
- 【アドバイス】食後に解熱鎮痛薬を服用しても、有効成分は吸収されます。胃への負担を減らすためにも、空腹時を避けて服用してください。
- 入浴前後だったので、服用をやめておいた
- 【アドバイス】基本的には、入浴前後に解熱鎮痛薬を服用しても問題ありません。ただし、体調や個人差によっては注意が必要なため、適切なタイミングでの服用を心がけましょう。
- お酒を飲む前や、飲んだ直後だったのでやめておいた
- 【アドバイス】飲酒前後は、解熱鎮痛薬は服用しないでください。アルコールが充分に体内から排出されたあとであれば服用可能ですが、排出にかかる時間には個人差があるため、飲酒翌日などでも充分な注意が必要です。
定められた用量を超えて服用してしまった場合
市販の解熱鎮痛薬は、薬ごとに正しい用法・用量が定められています(例:1回量2錠、1日3回を限度、服用間隔は4時間以上 など)。薬の本来の効能・効果を得やすくするためにも、必ず定められた用法・用量を厳守しましょう。
体質に合わない場合
市販の解熱鎮痛薬にはさまざまなものがありますが、日本の場合には単剤ではなく合剤(2つ以上の薬効成分が配合されたタイプ)のものもあるため、その配合が自分の体質に合わないという可能性もあります。医師や薬剤師、登録販売者などに相談しながら、自分に合った薬を探すことが大切です。
このようなときは
病院で医師に相談を
市販の解熱鎮痛薬を服用していて、以下のような状況にあてはまる場合には医療機関を受診することをおすすめします。
服用タイミングや用法を守っても薬が効かない
正しい用法・用量を守りながら市販薬を飲んでいても効果が感じられない場合や、効きが悪くなってきたと感じる場合には、他の疾患を含めた可能性も考えられます。特に「症状がひどくなっていった」「つらい痛みが続く」「いつもと違う痛みを感じた」などの場合には、医療機関を受診し、医師の診断を仰ぎましょう。また、めまいや体のふらつき、しびれといったように頭痛以外の症状が併発している場合も、必ず医療機関を受診してください。
尚、市販の解熱鎮痛薬を服用して効果が感じられないと、「飲み過ぎて、薬に対する耐性ができてしまったのでは」と心配する人もいます。しかし、基本的に市販の解熱鎮痛薬は、用法・用量を守って服用すれば、耐性ができにくいとされています。