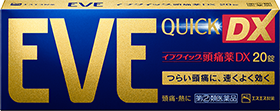激しい痛みがつらい群発頭痛の原因は?症状や治し方(対処法)も
群発頭痛は、
片頭痛や緊張型頭痛とは異なる特徴をもち、
発作のたびに生活を大きく乱すほどの
痛みを引き起こします。
それにもかかわらず、発症率が低く認知も充分ではないため、ただの頭痛として見過ごされるケースも少なくありません。
本コンテンツでは、群発頭痛の症状・原因・発作の特徴的なパターン、日常で気をつけるべきポイントをわかりやすく解説します。
群発頭痛の特徴
群発頭痛は、三大慢性頭痛(片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛)の中でも、もっとも痛みが激しいタイプとされています。まずは群発頭痛の症状や発生メカニズムからご紹介します。
群発頭痛の症状
群発頭痛は、片側の目の奥を中心とした激しい痛みが特徴で、数ある頭痛でもっとも強い痛みとされることがあります。痛みの質は「目をえぐられるよう」「ドリルで刺されるよう」と表現されるほどで、症状が重い場合には日常生活に支障をきたすこともあります。
痛みは一側性(いつも同じ側)で、こめかみや額、頬、あご、歯にまで放散することもあります。加えて、自律神経症状と呼ばれる目の充血・涙、鼻水・鼻づまり、発汗などの症状も伴うことが多く、「片頭痛」と混同されがちですが、痛みの性質や発作のリズムに明確な違いがあります。
特に注目すべき特徴として、以下のような発作パターンがみられます。
- ・発作は1日1~数回にわたり繰り返されることが多い
- ・1回あたりの持続時間は15~180分程度
- ・発作は1~2ヶ月間ほぼ毎日起きるが、その後は数ヶ月から数年、まったく症状があらわれない期間(寛解期)もある
また、性別や年齢にも傾向があり、20~30代の男性に多いとされています。
群発頭痛が起こるメカニズム
群発頭痛の発症メカニズムは、現時点で完全には解明されていませんが、発作時に目の奥の太い血管(内頸動脈など)の拡張や、その周囲の炎症反応が起きていることがわかっています。
また、近年注目されているのが、視床下部の関与です。視床下部は自律神経やホルモン分泌、体内時計の制御を担う重要な部位であり、群発頭痛の周期性や時間帯に一致する活動パターンがみられることから、体内時計との関係性が指摘されています。
加えて、発作時には顔面の感覚をつかさどる三叉(さんさ)神経が刺激されることで、激しい痛みが引き起こされると考えられています。
このように、群発頭痛は血管、神経、ホルモン、自律神経などが複雑に関係する多因子性の疾患であるとされています。

※イメージ図
国内での有病率は全人口の0.1%程度と推定されている
群発頭痛は非常に稀な頭痛疾患とされています。一般社団法人日本頭痛学会(※1)によると、日本国内での有病率は全人口の0.1%程度と推定されています。つまり、1000人に1人程度の割合でしか発症しないということになります。
※1 出典:一般社団法人 日本頭痛学会 群発頭痛の症状や発作発生時間の性差に関する研究
https://www.jhsnet.net/zutu_topics_74.html
その強い痛み、
群発頭痛かも……?
群発頭痛は発症頻度が低い分、「ただの片頭痛や疲れのせい」と誤解してしまうことが多い疾患です。その症状にはいくつかのパターンがあります。以下は、日本頭痛学会の「診療ガイドライン」(※2)をベースにした、群発頭痛の典型的な兆候です。
- ・「片側」の目の奥・こめかみに強烈な痛み
- ・症状が起こると、痛みでじっとしていられない
- ・一定期間、ほぼ毎日のように痛みがおとずれる
- ・痛みが起きた側の目が充血したり、涙がでる
- ・痛みが起きた側の瞳孔が収縮したり、まぶたが垂れ下がる
- ・側頭部や頬、あごや歯などにまで痛みが広がることも
- ・飲酒がきっかけとなって症状がおとずれることがある
複数当てはまる項目がある場合は、できるだけ早く頭痛専門医を受診することをおすすめします。
※2 出典:日本頭痛学会「頭痛の診療ガイドライン2021(改訂第3版)」
https://www.jhsnet.net/GUIDELINE/gl2013/215-238_4.pdf
群発頭痛の原因として
考えられること
これまでの臨床研究などを通じて、一定の発症傾向や誘因が明らかになってきました。ここでは、現在「群発頭痛の原因」として考えられている主な要素についてご紹介します。
気圧の変化
群発頭痛と気圧変化との関連性が指摘されています。具体的には、気圧が急激に下がることで、目の奥に走る太い血管(内頸動脈など)が拡張し、それに伴って血管周囲の神経が刺激され、激しい痛みを引き起こすというメカニズムです。
気圧の変化は、自律神経系にも影響を与えるため、もともと敏感な体質の人にとっては外的ストレスとしての気圧変化が発作の引き金となることもあります。
過度の飲酒・喫煙
群発頭痛の発作期において、アルコールが発作の引き金となることはよく知られています。なかでも、ビールや赤ワインなど血管を拡張させる作用のある酒類は要注意です。アルコールは血管を広げるだけでなく、神経伝達物質のバランスを乱し、脳内の血流や自律神経の調整機能に影響を及ぼすとされています。その結果、発作が起きやすい状態が生まれてしまいます。
また、喫煙も群発頭痛の発症と深く関わっているとされており、実際に患者の多くが喫煙歴を持つことが報告されています。タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は脳血管や神経系に悪影響を与え、発作のリスクを高める原因となります。
つまり、アルコールとタバコは、群発頭痛にとってまさに「火に油を注ぐ存在」であり、発作期には特に慎重な対応が求められます。
ホルモンの影響
群発頭痛は、体内のホルモンバランスの変動が発作に関与している可能性があると考えられています。なかでも注目されているのが、脳の視床下部に関連するホルモンの働きです。視床下部は、睡眠と覚醒のリズムを整えるメラトニンや、ストレス応答に関わるコルチゾールなどの分泌を調整する中枢であり、体内時計や自律神経と深く関係しています。
実際、群発頭痛は夜間に発作が起こりやすいという特徴があることから、こうしたホルモンの日内変動リズムと発症との関連性が指摘されています。
体内時計のずれ
群発頭痛は、夜間や睡眠中といった決まった時間帯に発作が集中する傾向があります。これは、体内時計(サーカディアンリズム)の乱れが発症と深く関わっている可能性を示しています。
体内時計は、脳の視床下部にある「視交叉上核(しこうさじょうかく)」という部位が中心となってコントロールしており、睡眠・覚醒やホルモン分泌、血圧、体温といった生理的リズムを整える重要な役割を担っています。
この体内時計が乱れると、視床下部の働きにも影響が及び、血管の収縮や拡張、神経伝達のリズムが崩れることで、群発頭痛の引き金となる可能性があると考えられています。例えば、不規則な睡眠習慣やシフト勤務、時差のある海外渡航、深夜の長時間スマホ使用などは、体内時計を狂わせる代表的な要因です。
これらが積み重なることで、発作のリスクが高まるとされています。
神経への影響
群発頭痛の発作は、外部からの刺激によって三叉神経や視床下部が間接的に刺激されることをきっかけに誘発されることがあります。例えば、熱すぎるお風呂やサウナ、過度な運動、急激な気温変化、強いにおいは、神経系にストレスを与えやすく、発作の引き金となる可能性があります。
特に発作期には、こうした刺激に対して神経が過敏になっている状態のため、普段は問題なかった行動でも突然激しい痛みを誘発することがあります。これらの外的刺激は、自律神経のバランスを崩し、血管の拡張や神経の過活動を引き起こす要因となるため、群発頭痛の対策や再発リスクの軽減を図るうえでは、できる限り避けたい行動といえます。
日常生活のなかでできる
群発頭痛への対策
群発頭痛は発症メカニズムが完全に解明されておらず、発作期に入ると市販薬では対処できないほどの痛みに悩まされることが多いです。そのため、まずは医療機関の受診をおすすめします。
日々の生活で発作の誘因を避ける工夫や発作の傾向を知るための記録が、医師との連携や早期治療に役立つ第一歩になります。ここでは、日常生活で意識すべきポイントを紹介します。
飲酒・喫煙を控える

群発頭痛の発作期には、アルコールが発作の誘因となることが知られています。また、喫煙に関しても群発頭痛との関連性が指摘されており、患者の多くが喫煙歴をもつことが報告されています。
神経への刺激となる行動を控える
発作期においては、普段なんともない行動や環境が神経への刺激となり、発作の引き金になることがあります。以下のような行動に注意しつつ、早めに医療機関を受診しましょう。
- ・熱い風呂やサウナに長時間入る
- ・強い香りの香水や柔軟剤を使用する
- ・気温や室温の急激な変化(真夏の外出・冬の屋外と暖房の行き来)
- ・辛い食事のとりすぎ
- ・過度な運動や興奮状態になる活動
規則正しい生活を心がける

特に睡眠リズムの乱れは、発作のタイミングと深く関係していると考えられているため、以下のような生活習慣を意識しましょう。
- ・毎日同じ時間に寝起きする
- ・深夜のスマホ・PCの使用を控える
- ・夜勤やシフト勤務の場合は、医師に相談し調整する
- ・昼夜逆転生活を避ける
症状の起き具合や期間について
記録をつけておくことも大切

群発頭痛は、発作の時期や時間帯に一定のパターンがあることが多く、日々の記録を残すことが発作の傾向把握と診断精度の向上につながります。次の内容を記録しておくと効果的です。
- ・発作が起きた時間帯や曜日
- ・発作が続いた時間の長さ
- ・痛みの部位(目の奥、こめかみ、歯など)や強さ
- ・併発する症状(涙、鼻水、まぶたの垂れ下がりなど)
- ・発作直前の行動や環境(飲酒・喫煙・ストレス・天候など)
- ・寛解期の開始と終了
こういった記録を重ねることで、発作のパターンが見えてくる可能性もあります。「春に多い」「深夜1時に繰り返す」といった傾向をつかめば、日常生活の中である程度の対処がとれるようにもなるでしょう。また病院を受診する際にも、患者自身が具体的な症状や経過を正確に伝えられるかどうかが、診断の精度を左右します。
群発頭痛において重要なのは痛みを我慢することではなく、その兆候に気づき、早めに医療機関へ相談することです。そのための第一歩として、日々の記録は非常に有効な手段です。
群発頭痛の診断や治療は
どのように行われる?
群発頭痛は自己判断や市販薬では対応できず、頭痛専門医による診断と治療が重要になります。診断は、国際頭痛分類(ICHD-3)に基づいて行われ、痛みの部位や持続時間、頻度、自律神経症状の有無などを問診で確認します。必要に応じてMRIやCTなどの画像検査も併用されますが、重視されるのは本人の症状記録と詳細なヒアリングです。
治療では市販薬の効果は期待できず、医師による処方薬による対処が基本となります。発作時には、スマトリプタンなどのトリプタン製剤の注射や点鼻薬、高濃度酸素吸入が有効とされ、発作への対策にはカルシウム拮抗薬や抗てんかん薬、ステロイド薬などが用いられることもあります。治療方針は、発作のパターンや体質に応じて個別に決定されます。
群発頭痛は一次性頭痛の一種であり、慢性化するリスクもあります。「いつもと違う痛み」を感じたら市販薬に頼らず、早めに医療機関を受診しましょう。