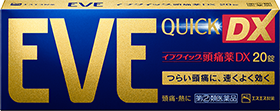朝から頭が痛い……起床時の頭痛の原因と対策
睡眠は、日中に働いた
脳や体を休ませる
大切な役割を担っています。
睡眠中に、脳では記憶情報を整理したり、また体では再生したりするのに必要な物質が分泌されています。それなのに「どうして起床時から不調があるのか」と不安に思う人も多いかもしれません。
本コンテンツでは「朝起きたときに頭が痛い」「午前中に頭痛が起きやすい」といった人へ向けて、睡眠に関する習慣や病気など一般的に考えられる原因を解説します。
「寝起きがつらい」「頭が重い」
起床時から頭痛に
悩まされている人も
軽度の頭痛で目が覚めてしまったり、起床時に頭痛を感じたりといった悩みをもっている人もいます。頭が締めつけられるような痛みの場合、心身のストレスや睡眠時の姿勢などに起因する寝起き頭痛(緊張型頭痛)かもしれません。
また、睡眠時の歯ぎしりや睡眠時無呼吸症候群など、他の原因が考えられる可能性もあります。ほかにも、朝起きてすぐに頭痛に悩まされ、仕事や家事、通学といった日常生活に支障がでる場合もあるでしょう。どのような種類の頭痛であっても、長く続いてしまう場合には自己判断せず、医療機関に相談することが大切です。
睡眠に関する習慣が原因で起こる
朝からの頭痛
睡眠は、日中の活動で蓄積された脳や体の疲れをとってくれるものです。しかし、場合によっては睡眠の質・量などに起因して、朝からの頭痛を引き起こしてしまうことがあります。その例をご紹介します。
睡眠時の姿勢
起床時の頭痛が緊張型頭痛の場合、まず考えられる原因として睡眠時の姿勢があります。緊張型頭痛は、同じ姿勢が長時間維持されることによって身体的なストレスが蓄積したり、血行が悪くなってしまうことによって起こる場合があります。
特に頭や首まわり、肩や背中にかけた筋肉が緊張することで生じやすい頭痛であることから、睡眠時に枕が高すぎたり低すぎたり、首や体が捻じれたりといった負荷がかかる姿勢が長時間続くと、筋肉の緊張によって起床時の頭痛につながってしまう可能性があります。
睡眠不足や睡眠過多
次に、睡眠不足や睡眠過多も起床時の頭痛の原因となりえます。そもそも睡眠時間は長くても短くても、片頭痛を起こすきっかけになります。それは、睡眠の過不足がホルモン分泌などに作用して頭痛が起きるのではないかと考えられています。
自分に合った、適切な睡眠時間をとるように心がけることが大切です。片頭痛にあたる症状の場合には、市販の鎮痛薬で対処を行うのではなく、医師の診断を受けることをおすすめします。
睡眠時間はどれくらいとればいい?
日本人の平均睡眠時間は6〜8時間といわれています。ただし、適切な睡眠時間の量については個人差があり、何時間以上といった基準を設けることはできません。日中に快適に活動できることを目安にしましょう。
寝すぎ・寝不足を改善するには?
まずは睡眠の質を改善しましょう。睡眠の質が悪いと寝不足はもちろん、充分な睡眠をとろうと寝すぎてしまう原因にもなります。
日中は日光を浴びる、適度な運動をする、睡眠前は入浴して体を温める、寝る前にスマートフォンやパソコンは使わない、快適な寝具を使うなど、できることからはじめましょう。
ブラキシズム(歯ぎしり・噛みしめ)
ブラキシズムとは、歯ぎしりや噛みしめのことで、睡眠中に起こるものを睡眠時ブラキシズムといいます。この睡眠時ブラキシズムによって、朝からの頭痛が起こる場合もあります。
明確な病気ではないが、
不調が原因で起こる朝からの頭痛
起床時の頭痛にはさまざまな要因・タイプが考えられますが、まずは一次性頭痛について解説します。
片頭痛
片頭痛は、緊張型頭痛や群発頭痛と並ぶ一次性頭痛の一種です。主に収縮した脳血管が急激に拡張することによって痛みが出現するという発症メカニズムが以前は主流でしたが、現在では他にもさまざまな要因が上げられており、多数の原因を持つ疾患といわれています。ただ、他の要因の可能性もあります。
緊張型頭痛
緊張型頭痛は、主に後頚部(首のうしろ、うなじの部分)の筋肉のこりによって血流が悪くなり、引き起こされることがある一次性頭痛です。
血流の変化は姿勢の大きな変更、つまり寝た状態から座っている状態に変わったり、立っている状態に変わったりする際に起こりやすいという特徴があり、起床時に行われやすい副交感神経から交感神経へのスイッチも関係してきます。
緊張型頭痛の診断は医師によって行われますので、一過性ではなく痛みが続く場合には、専門医の受診が必要です。
病気が原因で起こる朝からの頭痛
朝からの頭痛は、さまざまな病気によっても引き起こされる可能性があります。それぞれの疾患の説明については、一般的にみられる特徴の一部のため、これらに該当するかもと思われた場合は、早めに医師の診断を仰ぐことをおすすめします。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、眠っている間に何度も呼吸が止まってしまう病気です。この睡眠時無呼吸症候群の症状が早朝からの頭痛を引き起こす可能性もあります。
脳腫瘍
脳腫瘍は頭蓋骨の中にできる腫瘍の総称であり、脳そのものから発生する原発性脳腫瘍の他にもさまざまな種類があります。一般的にみられる症状として吐き気や嘔吐のほか、慢性的な頭痛が挙げられ、早朝からの頭痛も含まれます。
高血圧
高血圧は、血圧が慢性的に高いという病態です。肥満や過剰飲酒、精神的ストレスや運動不足などさまざまな要因で高血圧になる可能性があります。
高血圧ではない場合でも、寝起きには交感神経が活発になり基本的に血圧は上昇しますが、高血圧の場合には、血圧上昇の度合いが大きくなる「早朝高血圧」が起こりやすいとされています。この早朝高血圧が頭痛を引き起こすこともあります。
日常的に頭痛が多い場合は
すぐ病院にいくべき?
朝からの頭痛に限らず、原因不明の痛みやつらさが続くようであれば、信頼のおけるかかりつけ医や専門医を早めに受診することが大切です。
軽度の痛みの場合に、まずは生活習慣を変える、状況に合う市販の鎮痛薬を飲むなどしたうえで、それでも症状が続く場合は医療機関へ相談するという方法もあります。ただし、頭痛が長く続く場合、また症状がひどい場合にはただちに医師の受診をおすすめします。
朝からの頭痛のうち、一過性の緊張型頭痛や片頭痛であれば一般的に生活習慣の改善や鎮痛薬で対処できる可能性があります。しかし群発頭痛、睡眠時無呼吸症候群などといったさまざまな要因も考えられますので、長く頭痛が続く場合には医療機関へ相談し、必要に応じた対処をしましょう。