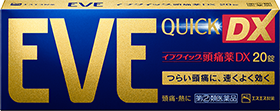解熱鎮痛薬(頭痛薬)の
飲み過ぎは良くない?
痛みを我慢せず、
上手に正しく解熱鎮痛薬を活用
一般的に頭痛薬と呼ばれる「解熱鎮痛薬」は、
正しい用法・用量を守って服用すれば
速やかに痛みをおさえられ日常生活の悩みや問題を
取りのぞくことができる頼れる味方です。
ただし、薬の飲み過ぎ(薬剤使用過多)が頭痛を引き起こしてしまう場合もあることを知っておきましょう。
頭痛薬を服用する人は、片頭痛か緊張型頭痛などの慢性の頭痛をもっていることがほとんどです。このような人には「薬剤性(薬剤使用過多による増悪を含む)による頭痛」が起きる懸念があります。
解熱鎮痛薬の飲み過ぎについて
一過性の頭痛などに悩まされている人にとって、市販の解熱鎮痛薬は日常生活における頼もしい味方です。用法・用量や、使用上の注意を守れば、体に過度な負担をかけることはありません。ただし、薬剤使用過多には注意が必要です。
解熱鎮痛薬の飲み過ぎが頭痛の原因になる?
つらい頭痛が起こると、痛みを早く鎮めたいと思うものです。特に大切な用事が控えていたり、育児や仕事の中で医療機関を受診する時間をとれないときは、我慢だけで改善を期待することが難しいため、症状に応じて市販の解熱鎮痛薬を服用することは有効です。不安なく薬を使用するためには、正しい知識を身につけておきましょう。
解熱鎮痛薬を過剰に服用すると、「薬剤性(薬剤使用過多による増悪を含む)による頭痛」を引き起こしてしまうことがあります。目安の1つとして「1か月に10日以上」の使用が挙げられますが、これに該当していなくても、頭痛の頻度や症状の強さが増すことがあれば、早めに医療機関へ相談しましょう。
なお、薬剤使用過多の症状は頭痛薬にかぎらず、鎮痛成分を含む風邪薬などでも起こる可能性があります。
「薬の箱や説明書を読まずに飲んでいる」という人は注意
市販の解熱鎮痛薬には、箱の裏面や同梱の説明書に以下のような事柄が記されています。
- ・効能 / 効果
- ・用法 / 用量
- ・成分
- ・使用上の注意(してはいけないこと、状況に応じて事前に医師などへ相談すべきこと)
- ・保管および取り扱い上の注意 など
解熱鎮痛薬を購入後、用法・用量だけを簡単に確認して飲みはじめ、「問題ないから大丈夫」と考えている人は注意が必要です。市販の解熱鎮痛薬の説明書には、例えば併用してはいけない薬(例、他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬等)などが書かれていますので、服用方法や注意点に目を通しましょう。
エスエス製薬の製品に関する説明書(添付文書)は薬ごとに閲覧、ダウンロードが可能です。
「市販薬の用法・用量を守っている状態では足りないと感じる」場合は危険
解熱鎮痛薬ごとに定められた用法・用量をきっちり守って服用しているにも関わらず、症状が治まらなかったり、頭痛の頻度や強さが増したりする場合には、医療機関への相談が必要です。
特に慢性的な頭痛のある人は、「薬剤使用過多」によってさらに症状がひどくなる可能性があることも知っておき、症状が良くならない場合は早めに医療機関を受診しましょう。
知っておこう
「薬の飲み合わせ・食べ合わせ」
基礎知識として、服用する薬によっては次のような飲み合わせ・食べ合わせがあった際に、問題が生じる場合もあることを覚えておきましょう。
- ・アレルギー薬や向精神薬とさまざまな薬の飲み合わせ
- ・牛乳やジュース、コーヒー、お茶やアルコールと薬の飲み合わせ
ただし、飲み合わせや食べ合わせについては薬によって異なりますので、特に問題がない場合もあります。まれに問題が生じる場合もある点を覚えておき、基本的にお薬は水またはぬるま湯で飲むようにしておきましょう。また、もし自分にトラブルが起こった場合には、医師に相談するようにしましょう。
【参考】鎮痛薬とカフェインの効用
コーヒーやお茶の成分として有名なカフェインですが、市販薬では眠気防止薬やかぜ薬、乗物酔い薬などに幅広く含まれるだけでなく、鎮痛薬にイブプロフェンなどの鎮痛成分の働きを助ける成分として配合されています。
カフェインは、頭痛に対して痛みの感受性を下げる働きがあります。また、セロトニンという物質によって脳血管が一時的に収縮した後に拡張することで発生する頭痛を、カフェインが脳血管を収縮させることで症状を緩和する作用もあります。お茶やコーヒーを飲むと頭痛が和らいだ経験のある人は、こういったことからきているかもしれません。
海外の試験では、抜歯後の痛みに対して鎮痛薬を単独で服用するよりも鎮痛薬とカフェインの両方を配合した製品の方が痛みにより効果があったとの報告もあります。鎮痛薬にカフェインも配合されているのは、こういった鎮痛効果を高めることを目指したことによります。
ただし、カフェインを過量に服用することによる健康リスクもあります。食品も含め、一日当たりの摂取許容量目安を考慮に入れて、カフェインのとり過ぎが心配な場合は、カフェインを含まない市販の解熱鎮痛薬の選択肢もあります。
解熱鎮痛薬(頭痛薬)の
飲み過ぎが心配なときは
基本的に解熱鎮痛薬は、早めの服用がポイントです。痛みがはじまったら早めに頭痛薬を服用することで、痛みのもとであるプロスタグランジンの生成をおさえ、痛みを効果的に和らげることにつながります。
「解熱鎮痛薬の服用をなるべく控えたほうがよいのでは? 」という考えで、もし痛みを我慢してしまうと、痛みを我慢している間にプロスタグランジンがさらに生成されてしまい、頭痛薬の効果があらわれにくくなってしまいます。また痛みがひどくなると脳が痛みに敏感になり、ちょっとした刺激でも痛みを感じてしまうことがあります。
痛みがあらわれたら早めに服用という基本的な使用のうえで、もし用法・用量以上につい飲みすぎてしまったり、前回いつ飲んだかわからないまま服用を重ねてしまったりした状況で痛みがひどくなった場合には、医療機関へ相談しましょう。
適切な薬剤・使用量・回数については医師に相談する
市販の解熱鎮痛薬で頭痛、あるいは痛みの症状に対処するときには、用法・用量に沿って服用すれば薬剤使用過多に起因する頭痛が引き起こされることは基本的にはありません。
ただし正しい用法・用量を守っている中でも万が一服用期間中に頭痛の頻度や痛みがひどくなった場合には、薬剤のせいよりもともとの疾患の悪化が考えられるため、服用中の解熱鎮痛薬の使用内容について医師へ相談しましょう。
薬剤の使用過多による頭痛を治療する場合には
万が一、薬剤使用過多に起因すると思しき頭痛があらわれてしまった場合には、医師に診断してもらいます。薬の服用をやめて症状の変化を管理したり、別の種類の鎮痛薬を処方されたりと医師の判断によってその後の治療方法が異なりますが、薬剤使用過多による頭痛は適切な治療により改善できます。
頭痛による生活の質を落とさないために解熱鎮痛薬を服用することは悪くありませんが、頭痛で鎮痛薬服用頻度が高くなっている人や鎮痛薬が効かなくなってきている場合には、一度、頭痛外来・脳神経内科・脳神経外科など頭痛治療を専門とした医療機関の受診をおすすめします。
特に片頭痛の場合には、最近新薬が登場して治療成績が向上していることもあり、積極的に受診することが望まれます。
どの医療機関を受診すべきか迷った際には、「日本頭痛学会」のサイトで認定頭痛専門医が確認できますので、ご参考ください。

監修:柴田 護先生
東京歯科大学 市川総合病院 神経内科 教授
慶應義塾大学 医学部客員教授
平成4(1992)年慶應義塾大学医学部卒業。
日本神経学会神経内科専門医・指導医、
日本内科学会総合内科専門医・指導医、
日本頭痛学会頭痛専門医・指導医、
日本脳卒中学会脳卒中専門医・脳卒中指導医、
日本認知症学会認知症専門医・認知症指導医。
※掲載している情報や、監修者の所属・肩書きは、記事作成時点のものです。