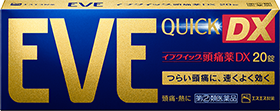片頭痛(偏頭痛)の症状や考えられる原因と予兆・前兆について
朝起きた瞬間から頭がズキズキと痛む。
光や音に過敏になり、仕事中も集中できずに
なんとかやり過ごしても、
夜には寝込むほどの痛みに襲われる。
そのような頭痛を繰り返していませんか?
実は、その痛みは「片頭痛(偏頭痛)」
の可能性があります。
本コンテンツでは、20代から50代の働き盛りに多い片頭痛について、症状の特徴や原因の他、予兆・前兆、そして日常生活でできる対策までわかりやすく解説します。
※医学的には「片頭痛(へんずつう)」が正しい用語ですが、一般的に「偏頭痛」も広く使われています。本コンテンツでは「片頭痛」を使用しています。
片頭痛(偏頭痛)の特徴
片頭痛は一次性頭痛の1つです。特に20代後半から40代の女性に多いとされる疾患ですが、30代から50代の男性にも十分起こりうる症状です。その痛みの特徴は、一般的な「緊張型頭痛」とは異なります。
片頭痛の症状
片頭痛の大きな特徴は、拍動性の痛みです。これは心臓の鼓動に合わせてズキズキと痛む感覚です。
痛みはこめかみや目の奥、頭の片側に集中することが多く、次のような症状を伴うのが一般的です。
- ・ズキズキと脈打つような痛み(拍動性頭痛)
- ・一般的に頭部の片側だけに痛みが起きるが、両側に痛みが生じる場合もある
- ・発作が始まると4〜72時間、強い痛みにより日常生活が困難になる
- ・吐き気や実際に嘔吐する場合もある
- ・光や音、においなどの刺激に敏感になり、暗く静かな部屋にこもりたくなる
- ・発作の最中は動くことで症状の悪化が考えられるため、横になって過ごす人も多い
このように片頭痛はただの頭痛とは異なり、発作的で生活を強く制限する症状が特徴です。
片頭痛が起こるメカニズム

※イメージ図
片頭痛の根本的な原因は、完全には解明されていませんが、現在有力視されているのは、「三叉神経の働きが異常に強くなってしまうこと」と「脳血管の拡張・炎症」が連動して起こるという説です。
まず、なんらかのきっかけで顔面や頭部の感覚をつかさどる三叉神経の働きが異常に強くなってしまうと、セロトニンをはじめとした神経伝達物質が大量に放出されます。このとき、脳内の血管は一時的に収縮しますが、セロトニンが代謝され減少すると、今度は反動で血管が急激に拡張し、周囲に炎症が起こります。
拡張した血管が、再び三叉神経を圧迫することで、拍動に合わせた痛みが発生します。さらにこの炎症と刺激は、脳の興奮状態を招き、吐き気や嘔吐といった自律神経系の異常を引き起こすと考えられています。
この一連の流れは、「小さなきっかけから大きな火種になる化学反応」のように連鎖的に発症します。頭痛の背景には、神経と血管の複雑なやりとりが隠れています。
原因は完全には解明されていない
片頭痛の発生メカニズムについては有力な仮説はあるものの、原因はまだ完全には特定されていません。ただ、片頭痛を引き起こしやすい体質や生活習慣には一定の傾向があります。
片頭痛(偏頭痛)の原因として
考えられること
片頭痛の原因は医学的にまだ完全には解明されていませんが、発作が起こりやすい体質や誘発要因(トリガー)には、いくつか共通点が見られます。ここでは、片頭痛の原因として考えられる要因をご紹介します。
心身のストレス
「真面目で努力家」「完璧主義」「神経質」といった性格の人に片頭痛が多くみられます。責任感が強く、心身の緊張を抱え込みやすいタイプの人は、自律神経のバランスを崩しやすく、それが片頭痛発作の引き金になる可能性があるためです。
また、女性の場合は月経周期と連動して症状があらわれることもあり、ホルモン変動が関係していると考えられています。
肩こり
肩や首の筋肉が過度に緊張すると周囲の血流が悪くなり、頭部への酸素供給がとどこおるため、神経が刺激されやすくなります。その結果、三叉神経が過敏に反応し、片頭痛を誘発することがあります。
また、肩こりは姿勢の悪さや長時間のデスクワーク、ストレスなどとも深く関係しており、慢性的な緊張状態が神経系のバランスを崩し、片頭痛の発作を招きやすくします。特に首の後ろから頭にかけた筋肉は頭痛との関連が強く、ここが硬くなることで痛みが誘発されるケースもあります。
喫煙
喫煙も、片頭痛を引き起こす要因の1つです。タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させる作用がありますが、血管が拡張すると拍動性の痛みが誘発されることがあります。また、タバコの煙に含まれる一酸化炭素や有害化学物質は、脳への酸素供給を妨げ、神経系に悪影響を与えることが知られています。
喫煙習慣がある人は、片頭痛発作の頻度や重症度が高くなる傾向があることも報告されており、受動喫煙でも同様の影響を受ける可能性があります。
カフェイン
カフェインには一時的に血管を収縮させる働きがあり、片頭痛の初期段階で適量にとることで症状を和らげる効果もあります。
注意すべきは、摂りすぎと離脱症状です。コーヒーやエナジードリンクを日常的に大量に飲むと、体がカフェインに依存しやすくなり、飲まない日には反動で血管が拡張してしまい、片頭痛が起こる可能性があります。
血管の拡張・収縮に影響する食べもの
特定の食品も、片頭痛のトリガーとなることがあります。特に血管の拡張や収縮を促す作用がある成分が含まれるものは、注意が必要です。以下が代表的な食品です。
- ・赤ワイン
- ・チーズ
- ・ハム
- ・サラミ
- ・チョコレート
- ・柑橘類
ただし、これらは絶対的な原因ではなく、個人差があります。日々、ノートにメモを残したり頭痛記録のツールとして知られる「頭痛ダイアリー」(※1)などを活用したりという方法で、自分にとってどの食品が影響しやすいかを把握することが効果的です。
※1 頭痛ダイアリー(一般社団法人 日本頭痛学会)
https://www.jhsnet.net/dr_medical_diary.html
天候・気圧の変化
天候や気圧の変化は自律神経のバランスを崩しやすく、片頭痛の誘発因子としてよく知られています。特に低気圧のときは、外部の気圧が下がることで体内の血管が膨張しやすくなり、脳の血管も拡張しやすくなります。その結果、片頭痛が引き起こされると考えられています。
また、急激な寒暖差や湿度の変化も体の恒常性を乱し、片頭痛を誘発する要因になりえます。最近では、気圧の変化を予測して通知してくれる「頭痛予報アプリ」なども登場しており、自分の体調と気象状況の関係性を可視化することで、対策に役立てられます。
まれに薬剤性(薬剤使用過多による増悪を含む)による頭痛の場合も
頭痛の頻度が高くなると、市販の鎮痛薬を常用してしまう人も少なくありません。しかし、この薬の使いすぎがかえって頭痛を慢性化させることがあります。1か月のうち15日以上頭痛があり、そのうち8日以上が片頭痛である場合、「慢性片頭痛」と診断される可能性があります。このような状態に陥る前に医師の診断を受け、薬の使用量を管理することが重要です。
思い当たりますか?
片頭痛(偏頭痛)が
あらわれる前の予兆・前兆
片頭痛は前触れなくはじまることもありますが、その前段階として予兆や前兆と呼ばれる症状があらわれるケースも報告されています。これらのサインを見逃さないことで、発作の前から対処をはじめられる可能性があります。
片頭痛の発作は4つの段階で進行する
片頭痛は、時間の経過とともに以下の4段階を経て進行します。
- 1. 予兆期:頭痛が始まる数時間〜数日前から、体や心に変化があらわれる
- 2. 前兆期:視覚・感覚・言語に異常がでる(※すべての人にあるわけではない)
- 3. 頭痛期:ズキズキとした拍動性の頭痛が起こる
- 4. 回復期:痛みはおさまるが、だるさや疲労感が残ることがある
特に予兆期と前兆期に注目することで、自分の片頭痛のパターンを把握しやすくなります。
【予兆期】倦怠感、だるさ
片頭痛の数時間〜数日前に、理由もなく倦怠感を感じることがあります。風邪の前兆のような感覚に近く、体全体に力が入らず、日常の作業も面倒に感じてしまう状態です。これは、脳内の神経伝達物質の変動によって、自律神経が乱れているサインと考えられています。
【予兆期】気分がなんとなくすぐれない、イライラする
精神的な変化も予兆としてよくみられる症状です。些細なことでイライラしたり、逆に落ち込んだりと気分が安定せず、周囲とトラブルになることもあります。これは片頭痛による神経過敏状態の前触れであり、感情のコントロールが効きにくくなっているサインです。
【予兆期】物事に集中しづらい
「頭がぼんやりして仕事に集中できない」「会話の内容が頭に入ってこない」といった認知のぼやけも片頭痛の予兆の1つです。脳の血流が一時的に不安定になることで、注意力が散漫になったり、短期記憶があやふやになることがあります。
【予兆期】普段以上に食欲がでる
片頭痛の予兆として、甘いものや炭水化物を無性に食べたくなることがあります。これは血糖値の変動やセロトニンの分泌異常と関係しているとされ、食欲増進が一種のバロメーターになっている場合もあります。反対に、食欲がまったくないという人もおり、個人差が大きいのが特徴です。
【予兆期】体がむくむ
顔や手足がむくんで重たく感じる場合、それも片頭痛の予兆かもしれません。ホルモンバランスや自律神経の変化が水分代謝に影響を与え、むくみとしてあらわれることがあります。特に女性は月経周期と重なることで症状が強まるケースもみられます。
【予兆期】首や肩がこる
肩こりや首の張りは単なる疲れではなく、片頭痛発作のサインである場合があります。特に後頭部から首にかけての筋肉が固くなると、三叉神経に影響を与えやすくなり、その刺激が発作を誘発する可能性があります。デスクワーク中心で働いている人は要注意です。
【予兆期】強い眠気を感じる、あくびが多くでる
睡眠時間に関係なく、「どうしても眠い」「あくびが止まらない」といった症状があらわれる人も多くいます。これは脳の覚醒レベルが低下している状態で、セロトニンの変動による脳内の刺激伝達が鈍くなっている影響と考えられています。
【前兆期】目の前で光のようなものがチカチカする
もっとも代表的な視覚前兆が「閃輝暗点(せんきあんてん)」です。視界の中にキラキラとした点滅やギザギザした光があらわれ、それが徐々に広がるのが特徴です。通常は数分から1時間以内におさまり、その後頭痛がはじまります。
【前兆期】ものがダブってみえる
視覚の異常として、ものが二重にみえたり、焦点が合いにくくなることもあります。これは視覚野への一時的な血流障害によるもので、空間認識やバランス感覚にも影響を及ぼすことがあります。
【前兆期】視野の一部が欠けて見える
視界の一部に「みえないゾーン」ができるケースもあり、新聞の文字の一部が抜け落ちたように感じることがあります。症状は一時的ですが、車の運転中や階段の昇降時には注意が必要です。
【前兆期】視野の一部にギザギザした歯車のようなものを感じる
「ギザギザ」「歯車のような形の光」など、非現実的なパターンが視界にあらわれるのも、片頭痛特有の前兆症状です。これは脳の視覚情報処理に一時的な異常が起こっているために発生します。
【前兆期】手足がしびれる
片側の手や足、あるいは顔の一部にしびれやチクチク感がでることがあります。これは「感覚性オーラ」と呼ばれ、視覚と並んでよく見られる前兆の1つです。まれに脱力感や麻痺に似た症状がでることもあるため、頻度が高い場合は医師の診断が必要です。
【前兆期】めまいがする
ふわふわとした浮遊感、ぐるぐる回るような回転性めまいなどを感じる人もいます。これは「前庭性片頭痛」と呼ばれるタイプの可能性があり、バランス感覚や内耳にも影響が及んでいることを示します。立っていられなくなるほど強いめまいがある場合は、無理せず安静にしましょう。
【前兆期】しゃべりにくくなる
片頭痛の前兆で、言葉がでづらくなったり、話そうとしてもうまく言葉が組み立てられないことがあります。これは脳の言語中枢の一時的な機能低下と考えられます。症状は数分から1時間程度で回復することがほとんどですが、失語症との区別が難しい場合もあるため要注意です。
日常生活のなかでできる
片頭痛(偏頭痛)への対策
片頭痛は薬による治療も重要ですが、日々の生活習慣を見直すことで対策できるケースもあります。特に片頭痛の発作には、生活環境や心身の状態が深く関与しているため、「自分でコントロールできる要因」を整えることがカギとなります。ここでは、今日からできる具体的な対策方法を解説します。
規則正しい生活を心がける
片頭痛の発作は、体内のリズムが乱れることによって引き起こされるケースが多くあります。そのため、「毎日決まった時間に起きて、決まった時間に寝る」「3食バランスの良い食事をとる」といった生活リズムの安定が、片頭痛対策にとって重要です。
特に朝食を抜くと血糖値の急降下をまねき、頭痛のリスクが高まります。また、寝すぎや夜更かしなどの生活の乱れも、敏感な人にとっては頭痛のきっかけになりえます。体調を日々安定させることが、長期的な対策につながります。
心身ともにリラックスする時間を設ける
精神的なストレスや緊張が続くと、自律神経が乱れ、片頭痛の発作を誘発しやすくなります。だからこそ、1日の中で意識的にリラックスの時間をつくることが大切です。
例えば、疲労が蓄積する前に、ソファーやベッドに身をあずけて、体の力を抜いてゆったりと過ごす時間を持ちましょう。それだけでも、筋肉の緊張がほぐれ、呼吸が自然と深くなり、自律神経が整いやすくなります。
また、深呼吸や瞑想、アロマ、ぬるめのお風呂など、自分にとって心地よいと感じる習慣を取り入れるのもおすすめです。就寝前にはスマホやテレビから離れ、静かな空間で過ごすだけでも脳の緊張が解け、深い睡眠につながります。
ストレスをためこまない
ストレスは片頭痛の引き金であるだけでなく、発作の回数や重症度が悪化する場合が考えられます。ストレスを完全になくすことはできませんが、「小出しにする」「上手に発散する」ことは可能です。
好きな音楽を聴いたり、自然の中を散歩したり、軽い運動を日常に取り入れるのも効果的です。趣味に没頭したり、友人との時間を楽しむことも、心のリズムを整える大切な手段です。スポーツやカラオケなど、気分転換になるアクティビティを取り入れてみましょう。
状況に応じてアルコールや激しい運動を控える
赤ワインやチーズ、チョコレートなど、血管を拡張させる作用をもつ食品や飲み物は、片頭痛を引き起こすトリガーになることがあります。特にアルコールは、血流を急激に変化させるうえ、睡眠の質を低下させるため、発作をまねきやすい要因の1つとされています。
また、激しい運動にも注意が必要です。健康のためにとハードなトレーニングを取り入れていても、発作が近づいているときには逆効果になることがあります。強度の高い運動は血管を一時的に広げてしまうため、片頭痛の引き金となることがあるのです。
特にお酒や運動のあとに片頭痛が起きやすいと感じている人は、その前後の過ごし方を見直しましょう。そうした体験の積み重ねから、自分に合った生活リズムがみえてきます。
つらい痛みが続く発症時は
片頭痛の発作が実際にはじまったときには、無理して我慢せず、早めに対処することが大切です。対策を講じるタイミングが早いほど、痛みの強さや持続時間を軽減できる可能性が高まります。次のような方法をぜひ実践してみてください。
-
静かな暗い場所で休む
光や音が刺激となり、痛みが強くなることがあるため、静かな環境に身を置きましょう。
-
痛む部分を冷やす
こめかみや後頭部など、ズキズキする箇所をタオルで包んだ保冷剤などで冷やすと、血管が収縮し痛みが和らぎます。
-
こめかみを短時間軽く押さえる
指先で軽くこめかみを圧迫することで、一時的に血流をおさえ、拍動性の痛みをおさえる効果が期待できます。
-
カフェインを適量とる
コーヒーや緑茶に含まれるカフェインには血管収縮作用があり、初期段階であれば効果を感じる人もいます。
-
鎮痛薬は早めに服用する
痛みが本格化する前の段階で鎮痛薬を服用すると、効果が高まることが多いです。ただし、頻繁な服用は「薬剤性(薬剤使用過多による増悪を含む)による頭痛」をまねくため、使用は月10日以内が目安とされます。
-
入浴、運動、マッサージは控える
発作中の入浴や激しい運動、マッサージは血管を拡張させ、かえって症状が悪化する場合が考えられます。片頭痛の発作時は温めず、体を冷やし、刺激を最小限におさえることが大切です。
頻繁に片頭痛が起こる、または市販薬が効かないほど痛みが強いという場合は、医療機関へ相談することをおすすめします。