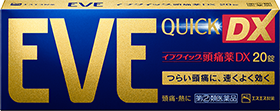頭痛の対処法(セルフケア)と管理
つらい痛みを和らげるために
頭痛に長期間悩まされている場合、
医療機関を受診することが大切ですが、
自分でも頭痛の基本的な知識を学んでおくと、
可能な範囲でセルフケアする場合に役立ちます。
本コンテンツでは、一般的に多くみられる「一次性頭痛」に関する基本知識と、セルフケアの方法などを紹介します。
- 頭痛の種類を正しく判断することが大切
- 頭痛の「痛みを和らげる」ためにできること
- 頭痛への対処として日常的にできること
- つらいときは試してみて!「緊張型頭痛を和らげるツボ」
- 用法・用量を守ったうえで頭痛薬(解熱鎮痛薬)を服用
頭痛の種類を
正しく判断することが大切
日常的に悩まされている頭痛が、どのような種類の頭痛の傾向にあるか、ある程度把握しておくことが大切です。病状の正確な診断は医師がおこなうものですが、ここでは頭痛の種類を判断するのに役立つ管理方法や、予備知識を紹介します。
頭痛について記録する

頭痛の症状は個人差が大きいため、自分の頭痛について、じっくり観察しましょう。日記のように、どんなときに、どのような痛みが起き、痛みはどれくらい続いたかなど、頭痛の様子を書きとめておくと対策がとりやすくなります。
例えば片頭痛持ちだと思っていても、時々緊張型の頭痛が起きていたり、ちょっとした生活習慣が頭痛のきっかけになっていたなんてこともあります。専用の頭痛ノートを作成するもよし、普段使っている手帳を利用するもよし。頭痛が起きたら忘れずに記録する習慣をつけましょう。
例)記録する内容
- ・頭痛が起きた日付、大体の時間帯、痛みが継続した長さ(時間)
- ・頭痛の詳しい症状(脈打つような痛み、重く圧迫感のある痛みなど)
- ・頭痛以外の症状(肩や首のこりを伴った、吐き気があったなど)
- ・頭痛の前に感じた症状(目がチカチカしたなど)
- ・薬を服用したかどうか
- ・生理があった期間
一次性頭痛
頭痛には、大きく分けて「一次性頭痛」と「二次性頭痛」があります。二次性頭痛は、例えば脳腫瘍やクモ膜下出血、脳卒中といった脳や頭部の病気の症状の一部としてでてくる頭痛であり、その要因となっている疾患について治療したり対処したりすることが重要であるため、ここでは主に「一次性頭痛」について解説します。
代表的な一次性頭痛には、以下のようなものがあります。
片頭痛
偏頭痛という表記も広く使われていますが、医学的には「片頭痛」が正しい名称です。主に頭の片側が痛むことに由来していますが、実際には両側性の頭痛を経験している人もいます。片頭痛の特徴はズキズキとした脈打つような痛みであり、吐き気を伴うこともあります。また、頭痛の前兆としてキラキラとした光を感じる場合があります。
比較的、男性よりも女性に多くみられる頭痛であり、脳血管の収縮や拡張のほか、生理周期に関連して片頭痛が起こるケースもあることから、女性ホルモンが関係しているという説もあります。
緊張型頭痛
多くの場合、後頭部を中心として頭全体に圧迫されるような、締めつけられるような痛みを感じます。片頭痛がズキズキとした拍動性であるのに対して、緊張型頭痛は主に非拍動性の痛み(脈打つ感じはしない痛み)です。
群発頭痛
一次性頭痛の中では、比較的症例の少ない頭痛です。群発頭痛は片側の目の周辺や、前頭部、側頭部にかけて激しい痛みを感じる頭痛です。原因はまだ分かっていませんが、目の後ろを通っている動脈の炎症や、体内時計などが関係しているのではないかといわれています。
特に夜間や睡眠中に頭痛が起こることが多く、発作時には頭痛と同じ側の目が充血したり、涙がでたりという症状もみられます。頭痛の頻度としては1日〜数日の間に長時間の痛みが何回も起こり、その群発期が過ぎると、ある程度の期間起きない、というケースが多くみられることも特徴です。
その他の一次性頭痛
激しい運動の後や暑い日の熱中症など、脱水状態で起こる頭痛や、お酒を飲み過ぎることで起こる二日酔いに伴う頭痛も一次性頭痛の一種です。
痛みが続く場合や痛みが激しい場合は、早めに医師へ相談
頭痛が起こる場面や痛みの特徴などがどのような頭痛のタイプに該当していたとしても、発作が一時的なものでなく長期化している場合や、激しい痛みを感じる場合には医療機関を受診することをおすすめします。医療機関では診察や必要に応じた検査のうえで、診断をおこなってくれます。
頭痛の「痛みを和らげる」ために
できること
代表的な一次性頭痛の痛みに悩まされているときに、おすすめの対処法を紹介します。
生理時の頭痛の場合
生理の周期に応じて、主に生理がはじまる前後に起こる頭痛は、片頭痛の可能性も考えられます。普段から基礎体温表をつけるなどして、毎月いつ頃に頭痛が訪れるのか自分のサイクルを知っておきましょう。
生理時の頭痛が起こりそうな日には、予定をあまり入れないようにしましょう。
頭痛への対処として
日常的にできること
日常的に一次性頭痛に悩まされていたとしても、例えば痛みを感じていないときに「予防」のつもりで、習慣的に鎮痛薬を飲むことは控えましょう。不必要に服用回数が増えてしまい、薬剤の使用過多による頭痛を引き起こしてしまう可能性があります。
日常的にできる頭痛への対処としては、以下のようなことがおすすめです。
規則正しい生活
忙しい日々を送っていて就寝時間がつい遅くなってしまったり、不規則な生活リズムが続いてしまっている場合には、可能な範囲で生活のリズムを整えることからはじめましょう。
睡眠は、日中に働き続けた脳や体を休ませる大切な時間です。睡眠の量(時間)や質が不充分な場合、さまざまな不調をもたらす場合があり、頭痛もその1つです。理想的な睡眠時間は一般的な目安として6〜8時間ともいわれますが、適切な睡眠時間には個人差があります。充分に体を休められたと感じられ、日中に快適に活動できることを1つの目安にしましょう。
また、規則正しい生活は、頭痛の原因となりやすい自律神経の乱れをケアすることにもつながります。日中に活性化する交感神経と、夜間に活性化する副交感神経のバランスをとるためにも、不規則でなく、またバタバタと慌ただしくしすぎない規則的な生活リズムを心がけるとよいでしょう。
ストレスをためこまない

片頭痛がある人には、頭痛を引き起こすなんらかのきっかけがあるといわれています。なかでもストレスが挙げられ、ストレスがあるときに頭痛が起きる場合が多くみられます。逆に「ストレスから解放されたタイミングで頭痛を感じる」場合もあります。
緊張型頭痛も同じく、心身的なストレスや疲労によって引き起こされることがあると知られています。忙しい1日の終わりには、くつろいだ姿勢で心身を休めたり、ゆったりとした入浴や、お好みによってアロマテラピーなどでリラックスする時間を設けるなど、自分にあったストレス解消法を見つけ、頭痛をなるべく遠ざけましょう。
首まわりの体操

毎日、数分間程度でも、腕や肩を軽く回す習慣を付けておきましょう。首の後ろの筋肉をほぐすことで、片頭痛を起きにくくしたり、発作の頻度を少なくしたりすることが期待できます。
また、運動不足や心的ストレス、疲れなどでこり固まった筋肉をほぐすことで、緊張型頭痛を和らげることにつながります。腕や肩を回して、ストレスや疲れでかたくなりがちな、首まわりの筋肉をほぐしましょう。
こんなとき、体操はNG!
- ・片頭痛の発生時
- ・激しい頭痛がある
- ・発熱を伴う頭痛がある
栄養をしっかりとる

マグネシウムやビタミンB2は、片頭痛の予防や発生頻度の軽減に有用という説があります。食事やサプリメントで意識してとるとよいでしょう。マグネシウムやビタミンB2が豊富な食材には、大豆や豆腐のほか、ひじき・ワカメなどの海藻類があります。
避けた方がいい食べ物はある?
一般的によく聞かれる話として、アルコール(特に赤ワインなど)、チョコレート、チーズ、ピーナッツ、豚肉などが片頭痛を引き起こすといわれることがありますが、人によって片頭痛を引き起こすきっかけや、その強さは異なります。アルコール以外の食べ物で頭痛が起きることは稀であったり、明確な因果とまではいえないという報告もあるため、あまり神経質になりすぎないようにしましょう。
なお群発頭痛の場合、発作が続いている時期は、飲酒や喫煙は避けましょう。
飲酒や喫煙を控える
アルコールや喫煙と頭痛との関連性についても諸説ありますが、お酒もタバコも、片頭痛や群発頭痛の原因となり得るものとして一般的に知られています。特に、頭痛の発作が日常的になっていて、飲酒や喫煙が多くなっている場合は、控えてみることをおすすめします。
つらいときは試してみて!
「緊張型頭痛を和らげるツボ」

緊張型頭痛がつらいときには、痛みの緩和が期待できる「ツボ」を適度に刺激してみるのも1つの手です。具体的には百会や風池、天柱、完骨、肩井などのツボを適度に刺激しながら、首や肩の筋肉の緊張をほぐすことがポイントです。
なお、頭痛の種類が片頭痛の場合には、頭や首まわりはあまりさわらずに、腕や足など、頭から離れた場所のツボを軽く刺激するか、温めるとよいでしょう。
用法・用量を守ったうえで
頭痛薬(解熱鎮痛薬)を服用
一次性頭痛のうち、軽度なものや一過性の痛みの場合には、市販の解熱鎮痛薬が有効です。
頭痛の種類によっては効能が期待できる
一次性頭痛のうち、特に片頭痛や緊張型頭痛の傾向のある軽度な頭痛の場合には、市販の解熱鎮痛薬を利用するのも1つの方法です。痛みのもととなるプロスタグランジンという物質の生成をおさえ、頭痛を和らげる効果が期待できます。
群発頭痛に該当すると感じられた場合には、専門医を受診し、指示に従いましょう。
過度の服用には注意
用法・用量や、使用上の注意を守って服用するかぎり、市販の解熱鎮痛薬は頭痛をお持ちの人にとって支えとなります。
しかし、例えば頭痛が起きていないうちに「念のため」と日常的に服用したり、漫然と連用したり、定められた用量以上の過度な服用があったりする場合には、薬剤の使用過多による頭痛を引き起こしてしまう場合があります。
不安なく薬を活用するために、解熱鎮痛薬の添付文書で正しい知識を得ましょう。
エスエス製薬の製品は、薬ごとに添付文書のダウンロードが可能です。