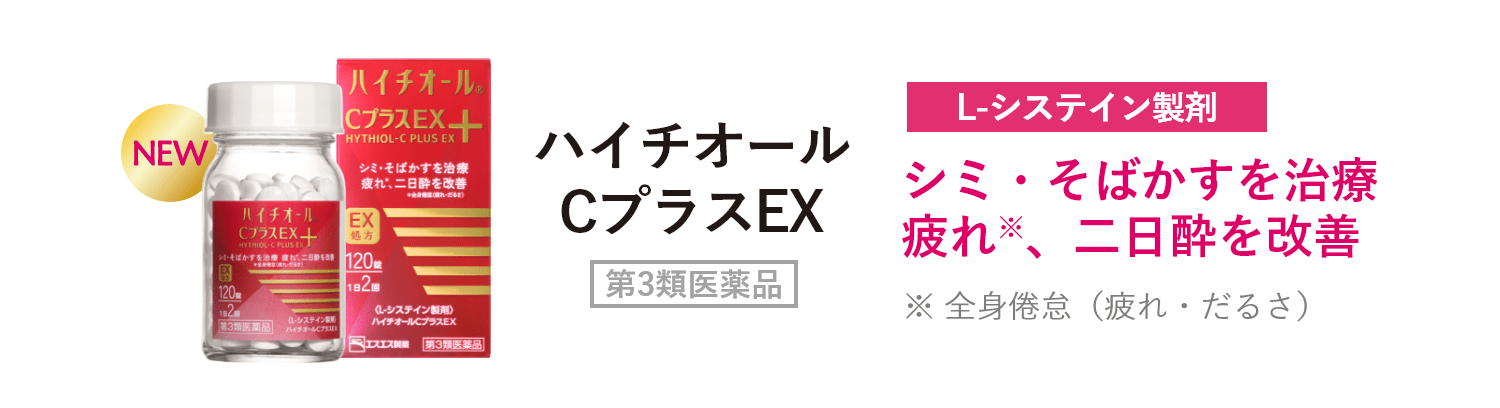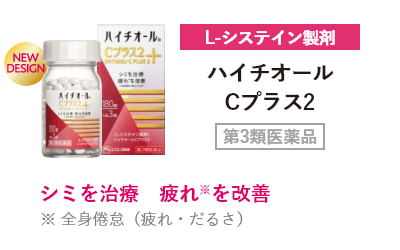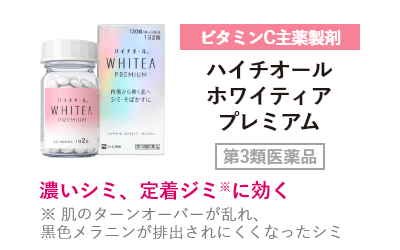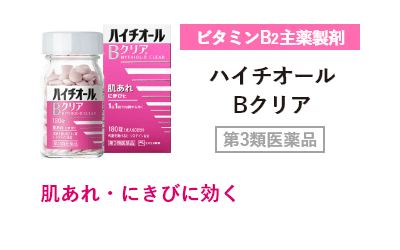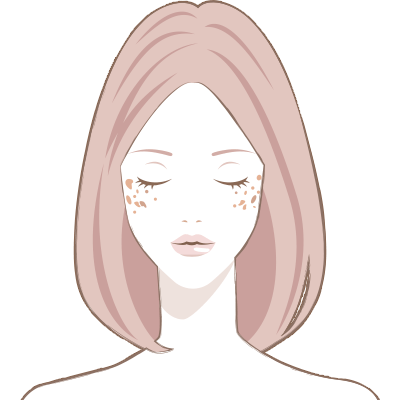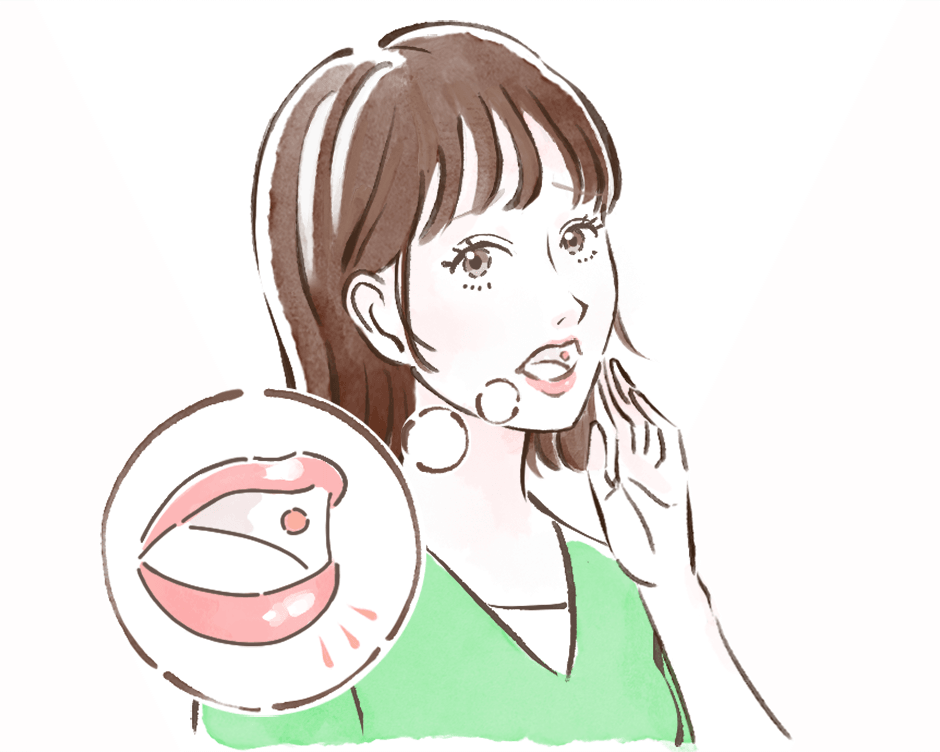口内炎ができてしまった時の対策と予防方法
口内炎は口の中のトラブルだけでなく、体の不調のサインでもあります。
できてしまった場合にすぐ対処することが大切です。また、繰り返さないように予防方法についても知っておきましょう。
口内炎ができるメカニズム
口内炎は、ストレスや栄養不足などで免疫力が低下し、口の粘膜の防御力や修復力が弱まることで起こります。免疫細胞のひとつであるT細胞が、何らかのきっかけで粘膜の細胞を攻撃すると、「サイトカイン」という炎症物質が放出されます。これにより、炎症が強まり、赤みや腫れ、痛みが生じます。特にTNF-αは炎症を悪化させ、痛みや潰瘍の形成に大きく関わっています。
また、口の中には普段バランスを保っている常在菌が多く存在しますが、免疫力の低下や口腔の乾燥、抗生物質の影響でそのバランスが崩れると、菌が増えて炎症が起こり、口内炎が発生・悪化することがあります。
口内炎の対策①:ビタミンをとる
ビタミンの中でも、ビタミンB群(特にビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₃、ビタミンB₅、ビタミンB₆)、ビタミンCを積極的にとることは、口内炎の対策に有効です。
できてしまった口内炎の治りが早くなるだけではなく、予防をすることができるので不足しないよう意識してとるようにしましょう。
それぞれどのような働きがあるか、また、どのような食べ物に含まれるのかをご紹介します。
- ビタミンB₁:皮膚や粘膜の健康を維持し、疲労回復・ストレス軽減の役に立つ
- 豚肉、うなぎ、たらこ、玄米、ごま、大豆、落花生 など
- ビタミンB₂:皮膚や粘膜の健康を維持し、代謝を助ける
- レバー、卵、納豆、サバ、イワシ、海藻類、きのこ類、はちみつ など
- ビタミンB₃:皮膚や粘膜の健康を維持する
- レバー、鶏むね肉、たらこ、まいたけ、鶏ささみ肉、落花生、びんちょうマグロ など
- ビタミンB₅:皮膚や粘膜の健康を維持し、免疫力をサポートする
- レバー、しいたけ、チーズホエイパウダー、納豆、たらこ、ヤツメウナギ、モロヘイヤ など
- ビタミンB₆:免疫機能のサポートをし、タンパク質の代謝を促進する
- レバー、チーズ、バナナ、マグロ、カツオ、ピスタチオ、アボカド など
- ビタミンC:抗炎症作用があり、免疫力を高める働きがある
- パプリカ、ブロッコリー、キウイ、レモン、キャベツ、さつまいも など
外食が続くとどうしても栄養バランスが乱れ、ビタミン不足になりやすくなってしまいます。また、口内炎ができると痛みであまり食べられなくなったり、味覚が鈍くなり食欲が落ちてしまうこともあります。
口内炎になってしまった場合には、市販の医薬品でビタミンなどを補い対処すると良いでしょう。
口内炎の対策②:生活習慣の改善
免疫力の低下が口内炎を招いてしまうことがあります。
生活リズムが崩れて寝不足が続くと、体の疲れがとれずに免疫力が下がってしまいます。
また、睡眠不足が続くとリラックスできる時間が確保できず、ストレスを溜め込みやすくもなってしまいます。ストレスを溜め込むことも免疫力の低下につながってしまうので要注意です。
口内炎ができてしまったら、あまり無理をせず睡眠時間をしっかりととり、上手にストレスを発散していきながら、心と体の疲れを溜め込まない生活をすることを意識してみましょう。
また、栄養バランスの整った食事をすることも口内炎の対策や予防に有効です。
特にビタミンB群やCを意識してとるようにすることで、口内炎を予防したり、できてしまった口内炎を早めに治したりすることができます。
自分自身の生活習慣が乱れているなと感じたら、睡眠・食事・ストレスのどれかひとつだけでも改善できるように、生活を見直してみてください。
口内炎の対策③:口腔内を清潔にする

歯垢や歯石によって細菌が繁殖しやすくなることも、口内炎の原因や悪化につながります。
普段から、食後の歯磨きを欠かさず行うようにしましょう。もし歯磨きがしづらい環境だったら、水でうがいをするだけでも効果があります。また、歯間ブラシやデンタルフロスを使用して、歯と歯の隙間の歯垢や食べかすも取り除き清潔にすると良いでしょう。それから、入れ歯や矯正器具を使用している場合には、こまめに洗浄するようにしてください。
口腔内の乾燥も意識しましょう。水分をしっかりとること、舌の筋肉を鍛えること、口呼吸をしないようにすることなどを意識してみてください。
口内炎の対策④:口腔内を刺激しない
直接的な刺激を受けると口内炎ができやすくなります。
歯磨きの時に力を入れすぎて口腔内を傷つけてしまったり、刺激が強すぎる歯磨き粉を頻繁に使用したりすることで、口内炎につながることもありますので注意しましょう。
また、やけどや食事中にほほの内側・舌を噛んでしまうことも口内炎の発症につながります。
慌てずに、ゆっくり噛んで食事をしてください。
できてしまった口内炎が気になって舌や手で何度も触ってしまうと、悪化してしまうことがあります。また、口内炎ができている時には痛みが強くなるような辛み成分を含む食べ物を控えるなどしてあまり刺激を与えないように気をつけましょう。
口内炎の対策⑤:医師に相談する
口内炎が繰り返し同じ場所にできる、口内炎が長く続くという場合には、何らかの原因があるかもしれません。自己判断で解決しようとせず、医師に相談することが大切です。
口内炎は体の不調を知らせてくれるもの。まれに重要な疾患が潜んでいる場合もあります。
矯正器具や入れ歯をしていて何度も口内炎を繰り返している方は、その器具が合っていない、もしくは不具合が生じている可能性がありますので、歯科医師に相談すると良いでしょう。
まとめ
口内炎ができてしまった時には、ビタミンを意識してとること、生活習慣を見直して睡眠不足の解消やストレス発散をすること、口腔内を清潔に保つこと、口腔内をできるだけ刺激しないことで対策をしましょう。これらは、口内炎を悪化させないために有効なだけではなく、口内炎を繰り返さないよう予防の効果もあります。
また、口内炎がなかなか治らない場合や、繰り返してしまう場合には、医師に早めに相談するようにしましょう。