天気の変化によって生じる頭痛や関節の痛みを「気象病」と呼ぶことがあります。中でも有名なのは「気候・気圧の変化による頭痛」です。「雨の日は頭が痛くなる」「季節の変わり目はよく頭痛がする」という経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このコラムでは、気候・気圧の変化による頭痛の原因やメカニズム、対処法についてわかりやすく解説します。気候・気圧の変化による頭痛について詳しく知ることで、つらい頭痛をできるだけ予防し、頭痛が出たとしてもうまく症状を和らげられるように対処していきましょう!
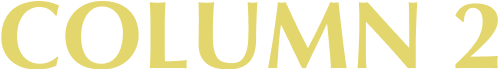
天気と頭痛の関係

季節の変わり目に増える“謎の頭痛”の原因は?気候・気圧の変化による頭痛の謎に迫る!雨の日や季節の変わり目に頭痛が起こるのはなぜ?
天気の変化で頭痛が起こるのはなぜ?
気候・気圧の変化による頭痛の原因はまだはっきりと分かっていませんが、気温、湿度、気圧の変化や降雨、強風などが頭痛と関連すると考えられています。
特に季節の変わり目は、天気が不安定になり、気温や気圧などが変動しやすくなることから、頭痛を訴える人が増えると言われています。
実際に、「頭痛の我慢※に関する5カ国調査」(エスエス製薬 プレスリリース:2025年6月公開)では、気候・気圧の変化で頭痛が発生することがよくある・たまにあると回答した人が7割以上となる結果となりました。
※頭痛の我慢:頭痛薬(市販の解熱鎮痛薬・医師の処方薬・漢方薬を含む)をすぐに飲まずに、痛みに耐える時間があること
気候・気圧の変化による頭痛のメカニズム
気候・気圧の変化による頭痛は、以下のメカニズムで起こると考えられています。
- 内耳(耳の奥にあり、平衡感覚をつかさどる器官)の気圧感知センサーが気圧の変化により反応する→自律神経の乱れが起こる→頭痛を発症
- 皮膚の温度センサー(TRPチャネル)が温度の変化により刺激される→頭痛を発症
- 季節や天気の変化によって脳の視床下部(自律神経の働きなどをコントロールしている部分)に影響を与える→自律神経の乱れが起こる→頭痛を発症
「痛みを我慢しない」ことが対策のカギ
頭痛が起きてしまったときには、市販の頭痛薬を早めに服用することで、痛みを和らげる効果が期待できます。「薬はあまり飲みたくない…」などと我慢していると、痛みの原因となるプロスタグランジンという物質が体内で増え、薬が効きにくくなってしまうことがあります。
上記で紹介した調査において「頭痛は我慢すべきでない」と考える人の割合が、日本・中国・ドイツ・イギリス・アメリカの5カ国の中で日本が最も多かったにも関わらず、実際は7割を超える人が頭痛を我慢していると回答しています。
また、頭痛薬を「服用しない」と回答した割合が日本では5カ国の中で最も多い結果となり、薬を使わずに我慢する傾向も明らかになっています。
頭痛は日常生活や仕事にも影響を与えることが多く、痛みに耐えているとかえって体に負担がかかることも。痛みを感じ始めた時点で早めに頭痛薬を使うのが、頭痛対策のポイントです。
気候・気圧の変化による頭痛が出やすいことが分かっている人は、天気の変化に基づいて頭痛の起こりやすいタイミングを確認できるスマートフォンアプリを活用するのも一案です。症状などを一緒に記録できるアプリもあります。「今日は頭痛が出やすい天気だ」「自分はこういうときに頭痛が出やすい」といったことが把握できて、早めに対処しやすくなるでしょう。
生活習慣の見直しもポイント
気候・気圧の変化による頭痛対策には、生活習慣を見直して自律神経を整えることも大切です。以下のような習慣を取り入れるようにしましょう。
- 自分に合った適切な長さの睡眠を確保し、規則正しい生活リズムを心がけることが基本です。寝不足も寝すぎも頭痛持ちの方には良くない習慣です。
- 入浴で体を温め、リラックスできる時間を持つことも効果的です。
- ストレッチや軽い運動を日常的に取り入れましょう。特に、腕や肩を動かして首周りの筋肉をほぐすことは予防にもつながります。
- 耳のマッサージもおすすめです。耳や耳たぶを回したり、やさしく引っ張ったりすることで血行が良くなります。ホットタオルで温めてから行うと、さらに効果的です。
- 寒暖差にも注意が必要です。夏はエアコンの風が直接当たらないようにし、冷え対策としてカーディガンやひざ掛け、腹巻などを活用しましょう。冬はマフラーや手袋、厚手の靴下などで“三首”(首・手首・足首)をしっかり温めることが大切です。
まとめ
気候・気圧の変化による頭痛は、気温、湿度、気圧などの変化によって内耳や皮膚にあるセンサーが刺激されたり、自律神経機能の変調が起こることで発生すると考えられています。
頭痛が始まったら、痛みを我慢せず、早めに頭痛薬を服用することがポイントです。特に気候・気圧の変化による頭痛が起こりやすい方は外出頻度の調整、薬の適切な服用、リラクゼーション、ストレスの要因の回避など早めの対処や、生活習慣の改善にも取り組みましょう。普段から自律神経のバランスを整える習慣を取り入れることが、気候・気圧の変化による頭痛の予防にもつながります。
- 監修
-
柴田 護先生
東京歯科大学 市川総合病院 神経内科 教授
平成4(1992)年慶應義塾大学医学部卒業。 日本神経学会神経内科専門医、 日本内科学会総合内科専門医、 日本頭痛学会理事、 日本脳卒中学会脳卒中専門医、 日本認知症学会認知症専門医。
※掲載している情報や、監修者の所属・肩書きは、記事作成時点のものです。
MAT-JP-2501264-3.0-08/2025|最終更新日: 2025年8月22日
